「答えのない闘い」佐藤天彦 叡王―PONANZA:第2期電王戦 二番勝負 第2局 観戦記
プロ棋士とコンピュータ将棋の頂上決戦「電王戦」。
電王戦への出場権をかけて初代叡王(えいおう)・山崎隆之八段、羽生善治九段らが出場した「第2期 叡王戦」を勝ち上がった佐藤天彦叡王と、第4回 将棋電王トーナメント優勝の将棋ソフト・PONANZAとの対局の様子を、生放送および観戦記を通じてお届けします。
■関連記事:
「人智を超えし者」佐藤天彦 叡王―将棋ソフト PONANZA:第2期電王戦 二番勝負 第1局 観戦記
序盤は何を指しても本当は悪くならない
朝、対局場へ現れた佐藤天彦叡王の表情は硬いものであった。白い着物が、その強張った表情をさらに際立たせているように思えた。顔は硬くとも、そこににじみでる勝負の前の棋士特有の気迫はなかった。それは、あるいは人間が前に着座していないということからくるものなのかもしれない。気合をぶつける相手がバーチャルなものというのは大変だろうな、と思った。

佐藤叡王の初手▲2六歩に対して、PONANZAが△4二玉を見て控室へ行く。「なんじゃこりゃ」と私がいうと、佐藤君の参謀である永瀬拓矢六段が「予定通りです」と答えた。すぐにすこし照れて「いや、正確にいうと予想した手のひとつです」と笑った。「いくつ予想したの?」「9手です」「へー」「△4二銀まで想定してました」「ほうー?」
2手目に△4二銀は、ソフトによって何でもありの感覚に慣れてきた私としてもさすがに驚いた。「それで悪くならないの?」永瀬君はまた照れた。「ええ、うまくバランスさえとれれば。まあ人間には無理ですけど」
そう、人間が、はっきりとソフトに教わったことがある。将棋は序盤は何を指しても本当は悪くならないこと。ただし、陣形のバランスをとるのが常に重要で、それが易しい局面を人間は好むこと。

▲3六歩から▲3七銀と今風に進めて、次の△5一銀(第1図)にはびっくりさせられた。うーむ、なんじゃこりゃ。だが意図はすぐに分かる。▲3五歩の攻めに対し△4三銀を用意したのである。

銀矢倉の形で受けの基本だ。それが見えにくい、というか意表なのは、序盤において金銀を引く手は悪手――おおげさにいえば論外という人間の先入観があるからである。
そこで▲1五銀から飛車先の歩を交換して駒組が進んだ。放送の局面を前に、永瀬君と私は確認し合った「先手、悪くないよね」ええと答える永瀬君は嬉しそうである。私も優秀な作戦参謀と意見が一致してなんだか嬉しい。

△6四角(第2図)の一手に我々は心の中でどよめいた。ここで角を手放すのはすこし意外なのだ。直感に反する、といってもいい。
局後、佐藤君に第2図で▲1八飛は考えなかったか訊ねてみた。「いや、ソフト、6四の角の位置大好きなんで」と答えがきた。なるほど、と思った。
▲1八飛は後手に角を手放させたことを「後悔させる」手だが、角を手放したことのショックが、「好きな位置だから」効果がないというのだ。角を合わせれば、十数手は「こんなもの」。両者とも工夫のしようがないので、するすると進んだが、それにしても早い。「PONANZAも早いねえ」と永瀬軍師にいうと「ええ、人間が考えると何かあるかと思って考えるんですが、こっちが早いと早いんです」という。まったく素晴らしい軍師なのである。
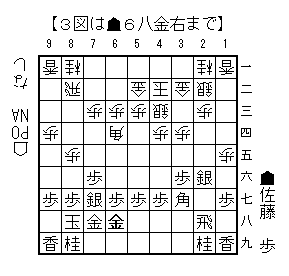
さーて第3図。この一手が敗着だって! この▲6八金右が悪手なんだって。ここから先はまあいろいろ粘りはあるが、どうも後手の勝ちなんだって。笑わないでくれ。呆れるのはいいが、怒ってこの画面に駒を投げないでくれ。この▲6八金右から穴熊にした構想がよくなくて、あとは不利、トップソフト的には、滅多に逆転しないんだそうである。
…分からん。…参りました。まったくことばもない。
どうやら穴熊というのは「AI的には」あまりよい戦法ではないらしい。たしかに人間にとって穴熊はいい。精神的なストレスがないのだから。

ソフトには恐怖心がない
余談を書くと、昔、大山康晴という将棋史上もっとも強かった棋士がいた。晩年、私が棋士になったころこういわれた。「先崎君、将棋というのは自玉から見るのよ、決して敵玉からみてはいけないよ」
このことばは単なる精神論ではなかった。次の一言がそれを証明している。「だって先崎君、自玉を目に入れれば、自然と敵玉が見えるでしょ。相手の玉から見たら、自玉は見えないでしょ」
意味は分かりますよね。大名人ともなるとさすがにいうことが違うのである。その大名人も穴熊の感覚にはついていけなかった。「穴熊は自玉を見なくていいんだから困ったもんだよなあ」といったのをきいたことがある。それでも六十九歳、死ぬまでA級を張ったのだが。
ソフト、AIには人間が穴熊をよしとするところの根底――恐怖心がない。ここが違う。ヒトが死を本能的に恐れるように、棋士は詰みを恐れる。詰まされる可能性がある王手は実にイヤなものだ。だから棋士は皆穴熊が好きだ。だが、どうも棋理的には――将棋の神の視点からみたら、穴熊はよい戦法ではないらしい。だからといってプロの人間同士の闘いにて穴熊が減ることもないだろう。所詮我々は人間だから。
しかし、やはりここで金を寄って穴熊にする手が敗着というのは棋士として辛い。マジメに考えると辛すぎてしんどいので、将棋がこれだけ強くなったのだから、AI様には愚かな人間の世界から戦争や貧困などをなくしてほしいなどと、ついベタなことを考えてしまう。
すくなくとも、人々の気持ちを明るくさせるために役立ってほしい。ん、役立てるのは人間か?
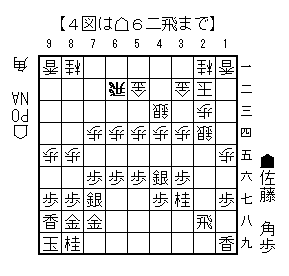
△6二飛とまわって第4図である。ここでは後手がよいらしい。たしかに。この△6二飛はさりげなくうまい手なのである。ここにも歩が8五まで伸びているから飛車を回るのは……、というさりげない盲点が隠れている。
ここからはどんどん差がついてゆく。評価値の差がついてゆくのである。点数でくっきりと出てしまう。
残酷な数字の真理を前に言葉も出ない。ファンの方はきっと分かり易くて楽しいと思うが、棋士としては……。モーツァルトの音楽を点数にされたら音楽家の方はどんな気持ちになるのだろう。

第5図の△7五歩はうまい手で、また評価値が上がったが、これは「筋」であって、盤の前にボヤーと棋士が座っていると気がついたら動かしている、というたぐいの手である。

第6図の△8六歩も「筋」である。局後に佐藤君は、「ここで何かなかったんですか」といっていた。隣で佐藤康光会長が黙り込んでことばを必死にさがしていた。空気が重いW佐藤を前に、私は「大差だったよ、数字がね」とおどけた。瞬間、佐藤天彦君の顔がパッと明るくなったのである。答えを知って安心したのだ。
そう、対局している本人だけ答えを知らない。ここに電王戦のおそろしさがある。後はAIどうこうではない。差がつくと拡がりやすいという将棋の本質そのままに大差の終局となった。
ソフトは人智を超えたのか?
本局の結果は大方のプロの、そして若手棋士の全員の予想と同じものであった。超えたかという「ことばのあや」については、電王戦終了という事実を持って皆様の想像力にゆだねたい。しばらくはAIと人間の対決は将棋界ではないだろう。

とりあえず総括してみると、人と人が闘う将棋は、1対1のマラソンのデッドヒートのようなものだなあ、と思った。理屈も理論もなし。相手に勝てばそれでよし。それが我々の生きてきた世界だ。
対して電王戦、AIとの対局は、お互い別々のところでタイムを計って答え合わせで勝ち負けを決めるというようなものだろう。それはそれでいい勝負ならおもしろいといえよう。
ここ数年は、奇跡的におもしろい数年間だった、という視点もあるのである。棋士としては、序盤の指し方に興味があった。コンピュータは、多種多様な指手を用い、将棋の序盤戦において、駒がぶつかるまでは、バランスさえ取れれば「なんでもあり」だということを教えてくれた。バランス重視にみえる人間のほうが、実は片寄った、偏見のある物の考え方としているということを知らしめてくれた。

棋士たちは、活発に多様な意見を飛ばし合った。そこで分かったのは、同じ棋士でもまったく皆違う感性を持っているということの確認だった。例えば、この文章ででた、永瀬君と佐藤康光君ではまったく違う将棋の見方をする。私はどちらかというと永瀬よりの感性である。人は、それが専門の分野においても感覚がまちまちなのだ。勝つという目的がはっきりしている世界ですらこうなのだから、現実の世界においては……。
ともあれ、これからは、棋士はコンピュータに教えてもらい、自分の技術を高めていく方向になるに違いない。個人的には、このおもしろい、そして二度とこない過渡期に1局指してみたかった。私は、おそらくもっともコンピュータと違う発想をする棋士である。指して、惨敗してみたかった。
時代がはじまったかと思うとすぐに終わってしまう時代である。とにかく、私は電王戦にて、知的好奇心が存分に満たされた。対局者の皆様お疲れさま。そしてソフトの関発者に心から敬意を表したい。
先崎学
※棋譜はこちらから
