ハリウッドが「同性愛」を認めるまでの歴史を5分で解説してみた――『ムーンライト』が『ラ・ラ・ランド』を押しのけてアカデミー賞を獲った理由
『WOWOWぷらすと』では「映画の中のセクシャリティ」に焦点を当て、映画評論家の松崎健夫さんが映画の中でLGBTの性はどのように描かれてきたのかを映画解説者の中井圭さん、ぷらすとガールズの福永マリカさんに解説しました。
松崎さんは、ハリウッドの歴史を振り返り、ゲイの黒人少年が主人公である『ムーンライト』が2017年度アカデミー賞を受賞するに至った背景を語りました。

―関連記事―
アニメの水着回・温泉回って実際テコ入れになっているの? ニコ生視聴者データを元に分析してみた
「『シン・ゴジラ』は東宝への宣戦布告」――庵野秀明に影響を与えた戦争映画の巨匠・岡本喜八を映画評論家が解説
サイレント映画の時代から存在していたLGBT

中井:
「映画の中でのLGBT」ということなんですが、出始めたのはいつごろなのでしょうか。
松崎:
『ラヴェンダースクリーン―ゲイ&レズビアン・フィルム・ガイド』という事細かに分析されている本があるので、ぜひ読んでみてください。
きょうは入り口としてお話を勧めていきたいと思うのですが、これは「映画が始まったときから」と言っても過言ではないんです。実際には1960年代になってからなのですが、サイレント映画の時代、エジソンがエミールとともに映画を作っていたじゃないですか。
そのときにエジソンの実験映画の中に男の人が抱き合って踊る映像があるんですよ。その映像自体があとから「ゲイブラザーズ」と名付けられたんです。あとは男が女の格好をする映像はその当時からありました。
たとえば1922年の『チャップリンの女装』というものがあるように、そういうものは昔からあったんです。ただしそのころは、「笑いのため」とか、「哀れみや恐怖の対象」として女装する人や同性愛が描かれていました。
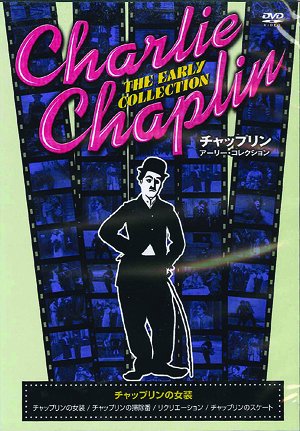
松崎:
そのあとは、最近ではトム・クルーズの『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』のメタファーというものはホモセクシュアルみたいなものがあるということで、映画が始まったころからそういった表現があったということで、直接的にはなかなか描かれなかった。吸血鬼自体がそういったメタファーではないかと言われていますね。
そして直接的に同性愛を描けないので、どう描いていたかと言いますと、『セルロイド・クローゼット』という1995年の映画があります。「クローゼットの奥に隠されている」というもので、そもそも「クローゼット」という言葉が同性愛者を指していたんです。
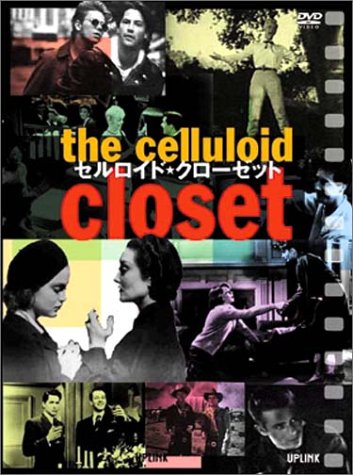
松崎:
1934年に『ワンダー・バー』という映画があって、カップルがお酒飲んできているところに男がやってきて、「ダンスをしませんか?」って誘う。するとカップルの女性は「わたし、彼氏がいるのに!」って思ってたんだけど、「キミじゃなくて、こっちの男性」と言って男をダンスに誘うというシーンがありましたね。『トップハット』の中でも、男性同士のダンサーの抱擁が映っている。
だから「そういう人たちがいますよ」というものを、同性愛者から見ればわかるというものが1930年代からちょこちょこ増えていったんです。それがもっとあとまで続いていって、たとえばヒッチコックの『ロープ』。

松崎:
これはどういうことで有名なのかと言いますと……。
中井:
カットですね。
松崎:
そう、81分を1シーン、1カットで撮られているかのように見える映画です。壁を移動するときに切って、それを繋いで81分やったのが有名な映画なのですが、これは実際の事件を原案にしていて、主人公の罪を犯した男性二人がそもそも同性愛者ではないかとにおわせるようなところがあった。当時からわかる人にはわかると言われていた映画です。
同年代で言うと、1955年の『理由なき反抗』というジェームズ・ディーンの映画で、サル・ミネオというキャラクターがいました。学校のロッカーで自分の髪の毛を女の子っぽく梳かすシーンがあって、しかもロッカーにアラン・ラッドの写真が貼ってあるんです。関係性を見ても、ジェームス・ディーンのことを好きなんじゃないかと見えるような作りになっています。
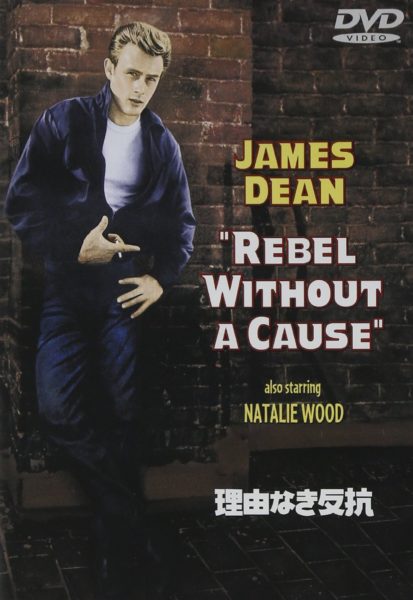
松崎:
他にも1960年代までには『ベン・ハー』とか『スパルタクス』の中にも、わかる人には「この人は同性愛者じゃないの?」というような演出があったりします。
LGBTの直接的表現を妨げた「プロダクション・コード」なる存在
松崎:
ではなぜ、そういう直接的な表現ができなかったかと言うと、これも理由があります。実は同性愛は自主規制されていたんです。ヘイズ・コード【※】というプロダクション・コード【※】があるんですが、それが1930年代にできて、60年代までずっと続いていました。
そういう表現をしたら世間から怒られたりとか50年代は「赤狩り」とかがありましたのでしょっぴかれる可能性もあったのでできなかったんです。
※ヘイズ・コード
アメリカ合衆国の映画における検閲制度。 アメリカ映画製作配給業者協会によって1930年に導入が決定され、1934年から実施された。
※プロダクションコード
1934年から1966年までハリウッド映画を規定していた規則
そもそも、この「プロダクションコード」ができるまでの動きとして、1930年代はギャング映画が台頭し始めたんです。でもギャング映画の主人公は犯罪者です。やっぱり「犯罪者が主人公とはけしからん」と言い始めた。「暴力を美化するのをやめよう」という政治的な運動が起こって、1930年に運用化されたものです。中には11の禁止事項と25の重要注意事項がありました。
どういうことがダメかと言うと、宗教の冒涜の禁止、殺人や犯行の細部を描く、中絶、売春、強姦、白人と黒人が交わること、出産もダメだしヌードもダメ。性的な抱擁もダメ、卑猥な言葉もダメ。口を開けたキスもダメ。
福永:
結構何もできないですね。
松崎:
そうそう。キスの表現も2、3秒までって決められていたんです。それでたとえばヒッチコックは映画の中で、2秒キスしたら離してしゃべって、というのを7分くらい繰り返して対抗したという話があって、アメリカは自由な国というイメージがありますが、映画の表現においてはずっと60年代までは規制があったんですね。
ゲイやレズビアンはクローゼットの中に入っている世の中には出てこない存在として扱われていたので、そういうものは、まったく出てこなかった。先ほども言いましたように「そういう人たちがいる」というような、におわせる描き方に留まっていたんです。

中井:
そのタブーはいつくらいから破られていったんですか。
松崎:
タブーでなくなったのは68年のプロダクション・コードがなくなった以降のことなのですが、50年代くらいから、ちょこちょこ出てきたんです。59年の二本の映画が公開されて、同じ女優が主演をしました。エリザベス・テイラーですね。
スタッフ:
え! そうなんだ!
松崎:
絶世の美女と呼ばれている人ですね。『去年の夏 突然に』と『熱いトタン屋根の猫』、二つともテネシー・ウィリアムズの戯曲を映画化したものです。
ポール・ニューマンと共演していて夫婦が性的にご無沙汰になっている話で、実は旦那がホモセクシュアルじゃないかというのが、見た人のほとんどがわかる映画です。自分の友達と関係にあったから夫婦感情が冷めているんじゃないかと見えるような作品。
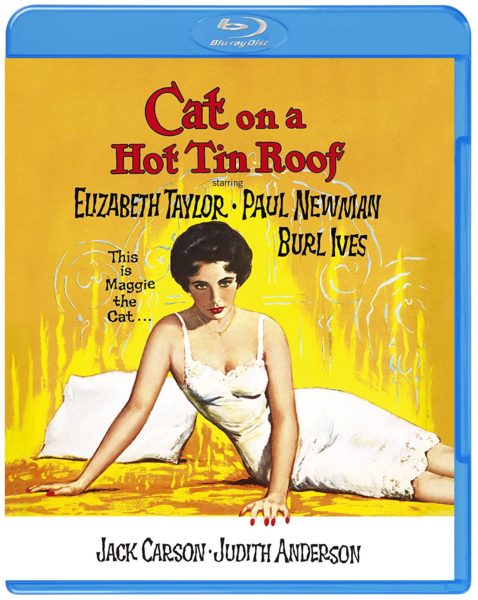
松崎:
『去年の夏 突然に』はキャサリン・ヘプバーンはアカデミー賞主演女優賞を4回取った人で、エリザベス・テイラーに名前のクレジットの順番を先に譲ったとしても当時話題になったのですが、この映画はキャサリン・ヘプバーンが息子を溺愛していて、エリザベス・テイラーの娘と旅行に行って、その先で死んじゃったという話。
自分の息子の死んだ姿を見ておかしくなっちゃって入院した。当時、ロボトミーという手術があったんですね。脳のある部分を切ったら精神疾患が治ると信じられていたんです。
この作品は「死んだ息子が同性愛者なんじゃないか?」ということと、「母親とも近親相姦にあったんじゃないか」、さらには人の肉を食うというものまで想像させるようなものを描いている。この映画が実は同性愛者であるというキャラクターを全面に出した最初の作品だと言われています。

松崎:
60年代に『ティファニーで朝食を』という映画がありました。オシャレ映画みたいに紹介されていますが、オードリー・ヘップバーン演じる主人公は「娼婦ではないか?」と言われています。でもそれだけではなくて、そもそも原作では主人公は10代なんですよね。
それを下に住んでいる作家志望の男が彼女のことを書いているという設定になっているんですが、彼が同性愛者ではないかというように描かれています。ところが映画の中では最後はこの二人がくっついて終わる。
もともとマリリン・モンローがやるとも言われていたのですが結局はオードリー・ヘップバーンになった。ではマリリン・モンローは何の映画に出たかと言いますと『お熱いのがお好き』なんですね。この映画はギャングに追われた二人が女装をして歌劇団に紛れ込んで逃げるという話です。
このとき「ゲイ」というものを描けないけれど、「世の中には女装している男性がいる」という認識があるからこそ、この映画は成立しているわけです。

松崎:
あとは『噂の二人』という映画あって、シャーリー・マクレーンとオードリー・ヘップバーンが周りから「レズビアンじゃないか」という疑いをかけられて悩むという話なんですが、シャーリー・マクレーンのインタビューを見ると、当時はそういうことが意図されている話だと気づかなかったと語っているんです。
そういうことを考えずに演じているんです。ところがほとんどの映画がカラーになっていた時代にもかかわらず、『去年の夏突然に』『お熱いのがお好き』『噂の二人』はモノクロなんです。これには理由があって女装した男をカラーで描くと、どぎついんです。だからあまりにも世の中に対して刺激が強すぎるから……という配慮があった。
スタッフ:
映画以外の小説だったり、お芝居のジャンルでは同性愛が普通に描かれていたんですよね。
中井:
なんで舞台は大丈夫で映画はダメだったのか気になります。
松崎:
これを『セルロイド・クローゼット』の中ですごく良い言葉で表現していまして、「男とは何か、女とは何かを映画は万人に教える力がある」。つまり最初、映画の中で同性愛者は「笑いの対象だった」というところから始まっていて、映画でそれを肯定されると「世間の人は世の中に出しちゃいけないものなんだ」と思ってしまったところからスタートしている。
そのまま半世紀きちゃったということですね。